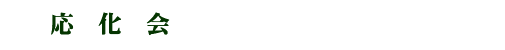![]()
平成28年度応化会会長、応用化学分野長、化学・生物工学専攻長
忍久保 洋
会長挨拶
 応化会会員の皆さまには、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。日頃より応用化学系教室の活動にご支援とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
応化会会員の皆さまには、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。日頃より応用化学系教室の活動にご支援とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
現在、応用化学系教室は大転換期の真っ只中です。来年4月から、工学部・工学研究科の改組により新学科・新専攻がスタートします(詳細は名大工学部ホームページをご覧ください)。残念ですが、この改組により「応用化学」という伝統ある名前がなくなってしまいます。具体的には応用化学分野と物質制御工学専攻、結晶材料工学専攻および未来材料・システム研究所(旧エコトピア科学研究所)の応用化学系研究室に加えて、生物機能工学分野の研究室がすべて合流し、学部レベルでは「化学生命工学科」という新学科に再編されます。これによって、工学部化学系研究室は明確な形で1つの学科を形成し、外部から見て大変分かりやすい構成になります。一方、大学院レベルでは「化学生命工学科」に属する各研究室がその専門性によって分かれ、「有機・有機高分子化学専攻」「応用物質化学専攻」「生命分子工学専攻」という3つの専攻を形成します。この変化にともない、カリキュラムの変更、入学試験の一本化、教室運営のすり合わせなど実に様々な課題が次から次へと湧いてきて対応に追われております。
このように常に何か落ち着かず、ばたばたしている中ではありますが、幸い応化教室は高いアクティビティを維持しております。教員や学生が多くの受賞の栄誉に浴しておりますので、是非一度応化ホームページでご覧ください。教員の異動では、本年3月に西山久雄先生がご定年を迎えられました。西山先生の応化教室への永年のご功績に対し篤くお礼申し上げます。また、永縄友規助教、兼平真悟助教、金日龍助教が転出されました。新天地での益々のご発展を期待しております。一方、松田亮太郎教授(H27.11、応7)、堀彰助教(H29.4、応7)、荒巻吉孝助教(H29.4、応6)、内山峰人助教(H29.4、応5)、馬運声特任准教授(H28.9、応7)、山下誠教授(H28.10、応4)、中村仁助教(H28.11、結5)が続々と着任されています。新進気鋭の若手新教授をお迎えし新しい研究室がスタートすることにより、応用化学系教室にも新たなエネルギーが注入され、力強く前進していけるものと信じております。
この工学部改組をさらなる発展へのチャンスと捉え、教職員・学生一同奮闘しております。学科再編により同窓会をどのように運営するかについても変化が予想されますが、応化会の諸先輩方々、卒業生諸氏におかれましては、今後とも旧応用化学系教室および新化学生命工学科への変わらぬご支援を今後ともたまわりますようお願いいたします。(平成28年12月13日)
平成27年度応化会会長、応用化学分野長、化学・生物工学専攻副専攻長
馬場 嘉信
会長挨拶
 応化会会員の皆さまには、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。日頃より応用化学系教室の活動にご支援、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。この場をお借りして、応化系教室に関連する近況をご報告させて頂きます。
応化会会員の皆さまには、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。日頃より応用化学系教室の活動にご支援、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。この場をお借りして、応化系教室に関連する近況をご報告させて頂きます。
応化系教室は、本学を世界屈指の研究大学に飛躍させるために、他部局とも協力して様々なプロジェクトに参画し、活動を拡げております。本学は、世界ランキングトップ100を目指すスーパーグローバル大学創成支援事業に採択されています。スーパーグローバル大学事業では、世界TOPレベルを目指す先端的研究強化のために、応化系教室の教員は、世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)において最先端研究を展開しています。さらに、スーパーグローバル大学の国際的な人材育成において、化学系グローバル30プログラムは、本年度初めての卒業生を輩出するなど、大学院生も増加しており英語のみの講義・研究指導が軌道に乗りつつあります。さらに、キャンパスアジアプログラムや名古屋大学交換留学受入プログラム(NUPACE)において、多くの学生が海外留学を経験するとともに、留学生の受入が活発に行われています。また、理学・生命農学研究科と協力した博士課程教育リーディングプログラムは、最初の博士課程後期課程修了者を輩出するなど、優秀な学生を化学・物理・生命系の分野から広い視点をもち俯瞰力と独創力をかね備え産学官にわたりグローバルに活躍するリーダーへと導いています。
さらに、産学連携を展開する未来社会創造機構において、応化系教室の卒業生および教員は、センターオブイノベーション(COI)拠点において、新しい産学連携研究開発を進めています。また、昨年度のノーベル物理学賞受賞を契機として、エコトピア科学研究所は、本年10月から未来材料・システム研究所として発展的に改組されており、応化系教員は、新研究所の中心的な役割を果たしています。キャンパス内ではこれらの建物の建設ラッシュであり、COIを進めるためのNIC館(National Innovation Complex)、WPIを進めるためのITbM(The Institute of Transformative Bio-Molecules)新棟が完成し、応化系の研究室が一部これらの新しい建物で研究のさらなる展開を進めております。
これらの研究・教育の成果により、応化系教室の教員・学生は、多くの受賞の栄誉に浴しております。このような諸活動が、今後、応化系教室のさらなる発展につながることを願っております。
教員の異動に関しては、本年、河本邦仁先生、小長谷重次先生が御定年を迎えられました。また、万春磊助教(H27.3、中国精華大学)が転出されました。益々のご活躍をお祈りしております。
新任教員として、村上裕教授(H27.4、応9)、藤野公茂助教(H27.7、応9)が着任され、新しい息吹をもたらしています。
以上のような動きに加えて、文部科学省が推進する国立大学改革プランを受けて、応化系教室も一つの転換期にあります。これを好機に捉えて、応化系教室の益々の発展をめざして、教職員・研究員・学生が一丸となって日々努力しております。今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。(平成27年10月9日受理)
平成26年度応化会会長、応用化学分野長、化学・生物工学専攻専攻長
上垣外 正己
会長挨拶
 応化会会員の皆さまには、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。日頃より応用化学系教室の活動にご支援、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。この場をお借りして、応化系教室に関連する近況をご報告させて頂きます。
応化会会員の皆さまには、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。日頃より応用化学系教室の活動にご支援、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。この場をお借りして、応化系教室に関連する近況をご報告させて頂きます。
本年度、工学研究科では、赤﨑勇特別教授・名誉教授と天野浩教授のノーベル物理学賞受賞で湧いておりますが、応化系教室周辺では、岡本佳男特別招へい教授・名誉教授が日本学士院賞を受賞され、大変喜ばしいニュースがございました。現役の教員・学生も日々研鑽を積み、多くの受賞の栄誉に浴しております。
大学の独立法人化以降、応化系教室は他部局とも協力してさまざまなプロジェクトに参画し、活動を拡げております。英語のみで卒業・修了可能なグローバル30プログラムは、平成26年秋に4年目に突入し、本プログラム初の4年生が研究室配属され、卒業研究を始めています。各学年の定員が数名程度と少ないですが、大学の国際化に貢献すべく英語の講義・指導に奮闘しております。中国・韓国の大学と共同運営するキャンパスアジアプログラムも4年目に入り、関隆広教授が中心となって進められ、留学生の派遣・受入が活発に行われています。また、博士課程教育リーディングプログラムも4年目に入り、理学および生命農学研究科と協力し、化学・物理・生命系の分野から広い視点をもちグローバルに活躍できる人材の育成に努めております。さらに、世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)においては大井貴史教授らが参画し、一方、未来社会創造機構においては応化系卒業生の江崎研司氏がセンターオブイノベーション(COI)拠点長に就任され、学内外から名古屋大学の研究活動を推進しています。キャンパス内ではこれらの建物の建設ラッシュであり、本年度中には完成予定です。このような諸活動が、今後、応化系教室のさらなる発展につながることを願っております。
教員の異動に関しては、守谷誠助教(H26.3、静岡大学講師)、永井寛嗣助教(H26.3、ダイセル)、山田篤志助教(H26.6、フランス国立科学研究センター)、飯田拡基講師(H26.8、島根大学准教授)が転出されました。益々のご活躍をお祈りしております。上木佑介助教におかれましては、H26.5にご逝去され、教室から心よりお悔やみ申し上げる次第でございます。
新任教員として、篠田渉准教授(H26.1、応1)、鳴瀧彩絵准教授(H26.1、結材5)、林幸壱朗助教(H26.5、エコトピア・ナノマテリアル)、藤本和士助教(H26.9、応1)、逢坂直樹講師(H26.10、物制6)が着任され、新しい息吹をもたらしています。
以上のような動きに加えて、文部科学省が推進する国立大学改革プランを受けて、応化系教室も一つの転換期にあります。これを好機に捉えて、応化系教室の益々の発展をめざして、教職員・研究員・学生が一丸となって日々努力しております。今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。(平成26年12月17日受理)
平成26年度理事長
服部 達彦 (S40)
平成25年度理事長
服部 達彦 (S40)
応化会正会員榊原定征氏、経団連次期会長に!
日本経済団体連合会(経団連)の次期会長に名古屋大学工学部応用化学科を昭和40年に卒業された榊原定征東レ会長が就任されることが決まりました。名古屋大学にとって、また工学研究科応用化学分野関連講座ならびに同窓会応化会にとって大変うれしいニュースです。
榊原氏は昭和42年に修士課程を修了され、東洋レーヨン(現東レ)に就職されました。平成14年から8年間、代表取締役社長としてカーボン繊維の事業化を推進し、東レの業績を回復されました。平成22年からは代表取締役会長として、現在に至っておられます。
名古屋大学との関連においては、全学同窓会の副会長を務めておられ同窓会の活性化に提言されておりますし、応化会との関連では平成23年10月、第2回応化会サロンの講師をお願し「ものづくり立国」としての基盤強化について講演していただきました。ご講演当時は東日本大震災から半年後、現在状況は変わってきていますが、これから正に日本経済の再生発展が期待される重大な時期に、経済界の舵取りという重責を担われることは大変ご苦労があると拝察します。理系、技術畑の経団連会長として持論を推進していただきたいと思います。健康の維持には十分ご注意頂き、益々のご活躍をお祈りいたします。 服部達彦 記(2014.01.14受理)
平成25年度応化会会長、応用化学分野長、化学・生物工学専攻副専攻長
西山 久雄 (S48)
会長挨拶
 応化会の皆様には、ご清祥のこととお喜び申し上げます。一言、ご挨拶申し上げます。新しい応化会ホームページが開設され1年余が過ぎました。若い会員の皆様にも興味をもっていただける応化会をめざし、会報のあり方もふまえてホームページのあり方を議論しつつ、新しい応化会の情報発信、運営方法に変えていく時が来ています。会報発行は、会費徴収の大きな役割を担っていますが、よりスマートな方法に変えていくことも必要です。住所録の整備も連動しています。すべては、会員の皆様への迅速かつより良い情報提供と同窓会活動の支援のためであります。理事会一丸となって努力している最中でございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。
応化会の皆様には、ご清祥のこととお喜び申し上げます。一言、ご挨拶申し上げます。新しい応化会ホームページが開設され1年余が過ぎました。若い会員の皆様にも興味をもっていただける応化会をめざし、会報のあり方もふまえてホームページのあり方を議論しつつ、新しい応化会の情報発信、運営方法に変えていく時が来ています。会報発行は、会費徴収の大きな役割を担っていますが、よりスマートな方法に変えていくことも必要です。住所録の整備も連動しています。すべては、会員の皆様への迅速かつより良い情報提供と同窓会活動の支援のためであります。理事会一丸となって努力している最中でございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。
さて、応化教室に目を向けてみますと、大学院博士課程エリート教育を目指したリーデイング大学院プログラムの設置、中国・韓国との連携教育研究を目指すキャンパスアジアプログラムの実施、学部・大学院で留学生を英語で教育するG30プログラムの実施など、打って出る施策を実行し教育研究の最先端を突っ走っています。また、応化ホームページをご覧いただきますように、教員の業績著しく河本先生の紫綬褒章受賞をはじめ数多くの受賞に驚かれると思います。応化系は学内でも高い教育研究に評価をいただいております。また最近の人事では、太田裕道先生が北海道大学教授(H24.9)、菊田浩一先生がエコトピア研究所教授 (H25.4)、梅村知也先生が東京薬科大学教授 (H25.4)、吉田寿雄先生が京都大学教授 (H25,4)、大井貴史先生がWPI研究所教授に就任されご活躍です。この10年余り7割近くの教授が定年で世代交替し、若手新准教授、新助教の採用や活躍もふくめ新しい応化教室として花が開き充実した時期を迎えています。さらに、これからの日本の化学工業会をしょって立つ博士を多く育て、国際性を備えた志の高い学士・修士を育てるべく努力をしておりますので、卒業生の皆様からより暖かいご支援をいただけますようお願い申し上げます。(2013.07受理)
平成24年度応化会会長、応用化学分野長、化学・生物工学専攻専攻長
河本 邦仁
会長挨拶
 応化会ホームページが設置されましたので、一言ご挨拶申し上げます。
応化会ホームページが設置されましたので、一言ご挨拶申し上げます。
昭和14年(1939年)に名古屋大学が創設され、応用化学科に最初の学生が翌15年に入学、17年(1942年)に卒業してから今年でちょうど70年が経過しました。その間、学科再編、教養部解体、四年一貫教育、大学院重点化、国立大学法人化などが時代の変遷に即して「大学改革」の名のもとに行われ、大学自体が文科省の施策に翻弄されながらも荒波を乗り越えて何とか現在に至っております。応化系教室関連でいいますと、各種研究施設、研究センター、研究所への設置協力、重点化後は複合専攻への一部進出、新設の創薬科学研究科への一部拡張等を行うなど、学内他部局、他専攻と協力して研究教育の充実に努めて参りました。また、他専攻、他研究科、他大学等と共同で文科省を中心とした種々の教育・研究事業を推進する中で、グローバルな人材育成にも力を注いでおります。
これまでに応化系教室から多くの卒業生が巣立っていかれ、国内外の様々な分野で活躍されています。応化会会員の集団が、社会・経済活動の少なくとも1%は支えているといっても過言ではないでしょう。応化教室の良き伝統を身に付けて社会で活躍できる人をより多く育てていくため、応化会では数年前から成績優秀な新4年生や修士修了者を表彰してエンカレッジしております。また、いろいろな催しを通して会員相互の交流と情報提供・交換を行っております。応化会会員である卒業生の皆様、教員会員の先生方には、応化系教室が世のため人のために役立つ人材を育成するインキュベータとしての役割を果たし続けられるように、これからも会員のネットワークをきちっと継承して応援していただけますようお願い申し上げます。(2012.05受理)
平成24年度理事長
服部 達彦 (S40)
理事長挨拶
 東日本大震災から1年余り経ちましたが、会員の皆様におかれましては直接被害に遭われた方、ご親族や友人が被害を受けられた方もおありになると思います。一刻も早く復興する様、祈念しております。
東日本大震災から1年余り経ちましたが、会員の皆様におかれましては直接被害に遭われた方、ご親族や友人が被害を受けられた方もおありになると思います。一刻も早く復興する様、祈念しております。
平成23年度は会報の発行が出来ず、真に申し訳ありません。種々の事情はありましたが、理事長としての指導力不足に起因しており、お詫びを申し上げます。
会報に同封して会費の振り込み用紙をお送りしていましたが、それも出来ませんでした。会費収入も23年度は予算の20%ほどと少なく、今後の運営に支障を生ずる状況になっており、応化会の立て直しが必要となってきました。
3月27日、4月17日、5月15日と立て続けに理事会を開催して、その対策を検討しております。5月19日に常議員会、東海支部総会、また、6月9日に本部総会、東日本支部総会、関西支部総会が予定されており、会員の皆様から忌憚のないご意見を伺った上で、6月12日に理事会を開催して、今後の運営方針、役割分担などを決める所存です。
先ず、皆様から頂いております各回便りなどの原稿をもとに、平成23、24年度会報の統合版を発行致します。9月頃にはお送りすることが出来ると思います。
会報については後述のホームページとも関連しますが、内容を見直し、必要最小限の記事を掲載することで、費用を抑えたものにしたいと思います。会報に同封して、会費の振り込み用紙をお送り致しますので、出来れば23、24年分を合わせてお振込みいただければ有難いと存じます。
もう一つは応化会のホームページを再構築し、公開することです。これまでにも出来てはいましたが、内容が更新されず、機能していませんでした。いろいろな経緯があり、応化教室のサーバーを応化会が使用させていただくことの是非が問題となったことがありましたし、その管理を誰が、どのように行うのかが明確に出来ないままの状況でした。
この度、名古屋大学大学院工学研究科 化学・生物工学専攻のホームページにリンクして、応化会のホームページを再構築出来ることになり、5月15日に公開致しましたので、これを利用して、応化会の状況をホットにお伝え出来るようにしたいと思います。応化教室のホームページも関心を持ってご覧いただきたいと思います。
応化会の会費収入が年々落ち込んできていることから、会員の皆様にもっと関心を持っていただける行事を企画しようと始めたのが、応化会サロンです。ワインを飲みながら寛いだ雰囲気で講演をお聞きし、懇親を深める趣旨で、若手会員の参加を期待しております。
第2回応化会サロンは平成23年10月21日(金)、講師に東レ株式会社 代表取締役会長の榊原定征氏を迎え、「ものづくり立国」としての基盤強化についてという演題でお話をお聞きしました。
以上、会報が発行できず、応化会の運営に支障を来たす状況になったことをお詫び申し上げ、またその立て直し策を決定、実行していくことをお約束して、理事長挨拶とさせていただきます。(2012.06受理)
平成23年度応化会会長、応用化学分野長
忍久保 洋
ごあいさつ
 東日本大震災から1年が経過しましたが、依然として日本全体への大きなダメージが見られます。被災地はもちろんのこと、被災地から離れていても企業等の活動に大きな影響があり、卒業生諸氏もその克服のために奮闘されているものと推察いたします。応用化学教室でも、夏の逼迫する電力事情から各研究室に節電を依頼し、一部の実験装置を停止するなどご不便をお掛けしました。
東日本大震災から1年が経過しましたが、依然として日本全体への大きなダメージが見られます。被災地はもちろんのこと、被災地から離れていても企業等の活動に大きな影響があり、卒業生諸氏もその克服のために奮闘されているものと推察いたします。応用化学教室でも、夏の逼迫する電力事情から各研究室に節電を依頼し、一部の実験装置を停止するなどご不便をお掛けしました。
さて、平成23年度は教員の異動が相次ぎました。これは、取りも直さず応用化学教室が高いアクティビティを維持していることをよく表しています。まず、大山 順也先生(薩摩研助教)、田浦 大輔先生(八島研助教)、加地 範匡先生(馬場研准教授)、安井 隆雄先生(馬場研助教)、原 光生先生(関研助教)、万 春磊先生(河本研助教)が着任される一方、渡慶次 学先生(馬場研准教授→北海道大学大学院工学研究院教授)、山本 芳彦先生(西山研准教授→名古屋大学創薬科学研究科教授)、永野 修作先生(関研助教→名古屋大学ベンチャービジネスラボラトリー准教授)、片桐 清文先生(河本研助教→広島大学大学院工学研究科助教)が転出されました。また、飯田 拡基先生(八島研助教→同講師)、浦口 大輔先生(大井研講師→同准教授)、伊藤 淳一先生(西山研助教→同講師)が昇任されました。さらに、応化教室に関係が深い先生として、Jiyoung Shin先生(G30プログラム担当特任准教授)、吉井 範行先生(計算科学連携研究センター特任准教授)、澁谷 正俊先生(創薬科学研究科山本研講師)が着任されました。
大きな変化としては、すべての講義を英語で行うコースである国際プログラム(G30)が昨年10月から、創薬科学研究科が本年4月からスタートし、研究教育の国際化・多角化がはかられることになります。さらに、関係諸先生のご尽力により、応用化学教室が深く関与するリーディング大学院プログラムおよびキャンパスアジアプログラムの両方が採択されるという快挙を達成しております。これらのプログラムは、大学院教育の重点化・国際化を一層促進するものであり、今年度から学生への様々な支援、海外派遣や、海外学生の受け入れなどが本格的にスタートします。
現在の困難な状況を打破するためには、何より日本のために踏ん張ってくれる優れた人材を輩出することが我々現役職員に課せられた使命であると認識し、教育研究活動を行っていきます。応化会の諸先輩方々、卒業生諸氏の応用化学教室への温かいご支援を今後ともたまわりますようお願いいたします。(2012.04受理)
平成23年度理事長
服部 達彦 (S40)
理事長挨拶
 平成22年6月より北野理事長の後任として、理事長をお引き受けすることになりました。
平成22年6月より北野理事長の後任として、理事長をお引き受けすることになりました。
昭和40年卒業で、東亜合成株式会社に勤務しておりました。
応化会との係わりは平成13年より17年まで監事を務め、平成20年より理事に就任しております。応化会の運営には種々の課題があり、その改善を図っていきたいと考えておりますが、何分浅学・非才でありますので、会員各位のご協力、ご支援をお願い致します。
第1の課題は応化会の運営を担当する役員人事に関して、平成19年までは名大の先生方が主体となって運営がなされてきましたが、応化会会員の先生方が大幅に減少して、一部の先生に負担が増大する問題が出てきました。そのため、学外の会員に役員を引き受けていただき、そのメンバーが中心となって、応化会の事業を企画・推進することになりました。
また、会長の人事についても昭和60年から斉藤肇先生が会長に就任されて以来、名大の教授あるいは名誉教授が会長となられ、本会の代表としてその役割を担っていただいておりました。しかし、会長をお引き受けいただく名誉教授の先生も少なくなり、応化会が発足した昭和44年から59年までと同様、応化教室の分野長の教授にその年度の会長をお引き受けいただくことが出来るよう会則を改訂いたしました。平成23年度は忍久保洋教授に会長をお願いすることになりました。
応用化学教室との連携を強化するため、関連講座を含め全ての教員に会員となっていただくこととし、従来の特別会員を教職員会員に改めております。まだ、この人事の問題について若干問題は残していますが、一応の体制は構築できました。
第2の課題は会費収入が年々落ち込んできていることです。10年ほど前には400万円を超える会費収入がありましたが、平成22年度決算では1,634千円に減少してきております。この年は年会費以外に寄付をお願いし、468千円もの寄付金を集めることができました。感謝申し上げます。
この会費収入が減少しているのは、特に平成年代に卒業した会員からの会費納入率が低いことが指摘できます。応化会の活動が若手会員の興味を引く内容に変革していく必要があり、これが第3の課題です。
先ず、応化教室の同窓会組織である応化会のことを学生さんに知っていただくために、応用化学教室から推挙された学部4年生、修士2年生に応化会賞を授与する制度を平成20年度に創設しました。
また、応化会会員、教職員会員を講師に招き、ワインを傾けながら気楽な雰囲気で講演をお聞きするサロン(応化会サロン)を始めました。第1回は平成22年10月1日(金)に平野前総長を講師に迎えて開催しました。若手の会員が出席しやすいように、金曜日の夕方、会社が終わってから集合できる時間に設定し、120名を超える参加者がありました。
応化会の会則もここの所毎年見直しを行っており、少しずつ改善してきていますが、会員数が増加し、行事も増えてきておりますので、簡素化という視点からも見直しをしていかなければとも考えています。
今後とも会員の皆様、特に若い世代の方からの建設的なご意見を頂戴したいと思いますし、応化会の各種行事への積極的な参加をお願いして、理事長挨拶とさせていただきます。(2012.04受理)
平成22年度応化会会長
伊藤 健兒(S38)
会長挨拶
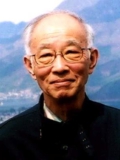 大学を取り巻く社会状況の大きな変動と、それに関連した応化教室の変化に対応できる応化会を目指して、柘植前会長と北野前理事長が進めてこられた改革を浅学菲才の私が引き継ぐこととなりました。服部理事長と私に課せられた任務は、お二人の示された方針に沿うように会則を改訂するとともに、新しい会則に則った運営に着手することでした。
大学を取り巻く社会状況の大きな変動と、それに関連した応化教室の変化に対応できる応化会を目指して、柘植前会長と北野前理事長が進めてこられた改革を浅学菲才の私が引き継ぐこととなりました。服部理事長と私に課せられた任務は、お二人の示された方針に沿うように会則を改訂するとともに、新しい会則に則った運営に着手することでした。
服部理事長はじめ理事の方々の熱心な理事会における議論を経て作成された会則改定案が、平成22年6月19日に大阪で開催された本部総会で承認されましたので、改訂項目のうち、重要な変更部分を抜き出して、会員の皆さまに説明させていただきます。詳しくはこの会誌の末尾にある応化会会則をご覧ください。
もっとも大きな変更は、応化会会長を、応用化学分野の分野長の先生(従来の教室主任に相当)にお願いすることにしたことです。いずれ正会員となる準会員の学部4年次学生・大学院生諸君と緊密に接する機会の多い分野長の先生が会長となることで、若い世代にとって応用化学系同窓会としての応化会を身近な存在に感じてもらうことを期待しての改訂です。これは目新しいことではなく、応化会が設立されてから、はじめの十数年間は、教室主任の先生が会長をつとめてこられた歴史がありますので、初心に帰ったと言うこともできます。
分野長に会長をお願いするにあたって、これまでは役員を正会員からのみ選出することとなっていた方式を、正会員または教職員会員(従来の特別会員を名称変更し、現職の応化系教員全員と希望する元教職員で構成)から選出できるように変更しました。さらに、ご多忙な分野長の応化会会長としての職務を大幅に軽減するため、従来会長が召集することになっていた総会・常議員会などの招集を、全面的に理事長に委任できることとしました。平成23年4月1日から就任されることになっています。
最後に私の非力のために、応化会の危機的財政状態への対策を何ら講じることが出来なかったことを皆様にお詫びするとともに、応化会が会員の会費によって運営されていること、現在の財務状況を改善するためには会費納入率を向上させることが必要不可欠であることを是非ともご理解いただき、会員の皆さまに毎年度の会費納入を、会長の最後のお願いとして強くお願いする次第です。
会長を退任するにあたり、服部理事長、北野前理事長、ご尽力いただいた理事の皆様、事務局の石田さんから賜ったご支援に厚く御礼申し上げます。
平成22年度応用化学分野長、化学・生物工学専攻専攻長
岡崎 進
ごあいさつ
 東北地方における未曾有の地震、津波災害には心を痛めるばかりでありますが、関係自治体や諸機関等も直後のショック状態から立ち直り、ようやく中・長期的な復興へと歩みが始まろうとしています。しかしながら、遠く離れたここ名古屋におきましても製造業等への影響は避けがたく、未だ通常の生産体制が回復できず、重苦しい空気につつまれているところであります。さらに、福島第一原発の状況を見ますと、当座の危機回避には何とか成功したように見えますが、安定的な廃炉までの道のりはさらに遠く、今後とも多大な努力を傾注していく必要があり、私ども技術者の責任は極めて重いものであることを痛感している次第です。応用化学卒業生の皆さんの中にも東北地方在住の方、そしてさらには原子力関係で日夜大変な努力をされている方々もいらっしゃることと存じますが、ぜひともこの苦難を乗り越えて頑張っていただきたいものと、遠くからではありますが心から祈念しております。
東北地方における未曾有の地震、津波災害には心を痛めるばかりでありますが、関係自治体や諸機関等も直後のショック状態から立ち直り、ようやく中・長期的な復興へと歩みが始まろうとしています。しかしながら、遠く離れたここ名古屋におきましても製造業等への影響は避けがたく、未だ通常の生産体制が回復できず、重苦しい空気につつまれているところであります。さらに、福島第一原発の状況を見ますと、当座の危機回避には何とか成功したように見えますが、安定的な廃炉までの道のりはさらに遠く、今後とも多大な努力を傾注していく必要があり、私ども技術者の責任は極めて重いものであることを痛感している次第です。応用化学卒業生の皆さんの中にも東北地方在住の方、そしてさらには原子力関係で日夜大変な努力をされている方々もいらっしゃることと存じますが、ぜひともこの苦難を乗り越えて頑張っていただきたいものと、遠くからではありますが心から祈念しております。
さて、平成22年度は応用化学分野におきましても大きな変化の年であり、大学の多様化、国際化へ向けて大きな一歩を歩み始めたと言えるでしょう。その一つがグローバル30と呼ばれる新しい斬新なコースの発足です。これは英語だけで学部、大学院の学業を修めることのできる外国人向けの正規のコースであり、応用化学分野も生物機能工学分野、そして理学部化学科と協力して化学プログラムを立ち上げ、その中の工学コースを担う主要な分野として大きな役割を果たそうとしています。平成23年10月から第1期生の新学期が始まりますが、担当の先生方の並々ならぬ努力のたまものとしてカリキュラム等の骨格は着々と確立しつつあります。現在は、新入学生の選抜と新規に雇用する外国人教員の選考に力を注いでいるところでありますが、どれだけ優秀な学生を集められるかという人的な要素こそが新しいコースの成否を決定する重要なファクターであり、この意味で、現入試実施委員長の確固たるお考えの下、応用化学は化学プログラムの工学コースにおいて相当にハイレベルの厳しい選抜を行ってきていると自負できます。新しいコースの確立は私ども教員にとっては大変なことではありますが、ぜひとも応用化学の新しい発展としてご期待いただければと存じます。
また、大学の多様化という側面においても、新研究科の設置へ向けての協力体制の確立や文科省の新政策であるリーディング大学院構想への提案など、応用化学分野はアクティブな展開をしてきております。そして何よりも、地に足をつけた方向として、多額の外部資金を獲得しながら日々活発に研究を進めてきています。
このように、応用化学は名大の中でも群を抜いた“元気さ”を発揮しながら教育研究活動を行ってきていますのが、これもひとえに応化会のOBの諸先輩方々、そして若手の卒業生諸君のご活躍と応化へのご支援のたまものであると認識しており、この欄をお借りして心からお礼申し上げたいと存じます。
以上、簡単ではございますが、ごあいさつ申し上げます。